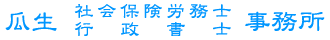2025/08/02
最低賃金 全国平均6%前後の引き上げ方向で調整
最低賃金の引き上げの目安について話し合う厚生労働省の審議会は、今年度は全国平均の時給で6%前後の引き上げとする方向で議論を進めていることが分かりました。額にすると63円前後で過去最大の水準となり、この水準で引き上げられればすべての都道府県で最低賃金が1000円を超えることになります。
企業が労働者に最低限支払わなければならない最低賃金は、現在、全国平均の時給で1055円となっていますが、今回の水準で引き上げられれば、全国平均の時給は1100円を超え、現在、最低賃金が900円台の31の県を含めてすべての都道府県の最低賃金が1000円を超えることになります。
2025/07/23
雇用保険の基本手当日額が8月1日から変更に
厚生労働省は、本年8月1日から雇用保険の「基本手当日額」を変更します。
雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配することなく再就職活動できるよう支給するものです。「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。
今回の変更は、令和6年度の平均給与額が令和5年度と比べて約2.7%上昇したこと及び最低賃金日額の適用に伴うものです。具体的な変更内容は以下のとおりです。
1基本手当日額の最高額の引上げ
(1)60 歳以上65 歳未満 7,420円 → 7,623 円 (+203円)
(2)45 歳以上60 歳未満 8,635円 → 8,870 円 (+235円)
(3)30 歳以上45 歳未満 7,845円 → 8,055 円 (+190円)
(4)30 歳未満 7,065円 → 7,255 円 (+190円)
2基本手当日額の最低額の引上げ
2,295 円 → 2,411円(+116円)
2025/07/01
現在の健康保険証が失効後も来年3月まで受診可能に
マイナンバーカードと一体化した「マイナ保険証」への本格移行に伴い、本年12月1日の有効期限切れで失効する従来型の健康保険証での受診について、厚生労働省が暫定的に来年3月末まで使用を認める方針であることが分かりました。マイナ保険証への切り替えなどを熟知していない高齢者らが保険診療を受けられず、医療現場が混乱する事態を防ぐ必要があると判断したようです。
マイナ保険証の利用率は5月末時点で29.30%にとどまっており、同省担当者は「医療現場の柔軟対応を認める」としていますが、期限切れ保険証の使用を認めることは、マイナ保険証の普及がさらに遅れる要因になる可能性もあります。
これまでは本格移行に伴い、保険診療を受けるには原則としてマイナ保険証か、マイナカードを持っていない人に発行される「資格確認書」を提示する必要があるとしていました。従来型の保険証が使用できるのは最長で12月1日までで、多くの自治体では自営業者らが入る国民健康保険の保険証が8月から順次失効します。
ただ、高齢者らの間で混乱も予想されることから、患者が期限切れの従来型保険証のみを持参した場合でも、一定の負担割合で保険診療を受けられる暫定対応を取ることにしました。期限切れ保険証を持参した患者には、次回以降マイナ保険証や資格確認書で受診するよう医療機関を通じて呼び掛けることとしています。
2025/06/30
中小企業の正社員賃上げ率4.03% 実施しない企業も
日本商工会議所は、「中小企業の賃金改定に関する調査」集計結果を発表しました。全国の会員企業を対象に調査したもので、2025年4月14日から5月16日にかけて行い、3,042社から回答を得ました。
定期昇給とベースアップを合わせた正社員の賃上げ率は平均で4%を超えましたが、一方で、賃上げしない企業も全体の2割に及び、二極化の傾向がみられるとしています。
2025年度に賃上げを実施した企業(予定を含む)は69.6%と、前年より4.7ポイント低下しました。20人以下の小規模企業では57.7%で5.6ポイント低下しています。
また、現時点で「未定」との回答は23.5%で3.1ポイント上昇。価格転嫁の遅れや米国関税措置等で先行き不透明感を懸念する声もあり、昨年に比べ「未定」の回答が増加しています。
なおパート・アルバイトの賃上げ率は5.21%、昨年比0.78ポイントの上昇でした。
一方、20人以下の小規模企業では、賃上げ額は37.4円、賃上げ率は3.30%で、昨年より0.58ポイントの減少となっています。
賃上げ率は全体では4%を超えるなど、中小企業も賃上げに最大限努力していますが、小規模企業は全体と比較し賃上げ額・率ともに低位となっていることからより重点的な支援が求められます。
2025/06/18
死傷災害4年連続で増加 60歳以上が3割に
労働災害による休業4日以上の死傷者数が4年連続で増加したことが、厚生労働省の「令和6年の労働災害発生状況」で分かりました。高年齢者の労災が増え続けており、死傷者数に占める60歳以上の労働者の割合が初めて3割に達しました。
令和6年1~12月における労災死亡者数は、前年比9人減の746人で、前年に続き過去最少を更新しました。業種別では、建設業が232人で最も多く、前年比9人増加。次いで製造業が同4人増の142人となっています。休業4日以上の死傷者数は13万5718人で、前年比0.3%増加しました。
死傷者のうち、60歳以上の人は4万654人でした。全死傷者に占める割合は前年比0.7ポイント増の30.0%で過去最高となっています。
2025/06/01
年金改革法案が衆院本会議で可決 基礎年金の底上げ明記
衆院本会議は年金制度改革法案の修正案を可決しました。
修正案は付則に基礎年金の底上げ策を明記しました。厚生年金の積立金を原資に基礎年金の給付水準を底上げすることにしています。具体的には2029年に財政検証を踏まえて底上げの実施を判断する予定です。
また一定の収入を得ながら厚生年金を受給している人を対象とする「在職老齢年金」も、現行制度では65歳以上の高齢者は厚生年金と給与の合計が月50万円を超えると厚生年金の受給額が減りますが、改正により月62万円までなら満額を受け取れるようになります。
2025/05/22
ハローワークに求人出しても9割が空振り(求職者とのミスマッチ拡大)
企業がハローワークに求人を出しても大半が採用に結びついていないようです。厚生労働省によると2024年は採用割合が11.6%と過去最低で、求人のおよそ9割が空振りでした。民間の人材サービスの拡大に加え、企業と求職者の間のミスマッチが広がっていることが窺えます。
厚労省は1963年からハローワークへの新規求人件数のうち、採用につながった割合を公表しています。60年代半ばは50%近くに達していたものの、その後は低下傾向にあり、近年はリーマン危機後の2009年の31.9%をピークに急低下しています。
もともと景気が良いときは比率は下がる傾向にありますが、近年の低下傾向は景気以外の要因も絡んでおり、民間のサービスを使って職探しをする人が増えていると厚労省は見ています。
2025/05/10
ハローワークのネットサービスにAI活用 厚労省が実証実験
ハローワークの求人情報をインターネットで申し込んだり検索したりすることができるサービスについて、厚生労働省はAIを活用して利用者からの問い合わせに自動で回答することができないか実証実験を行うことになりました。
インターネットを使ったハローワークのこのサービスは、働き手を求める企業からの申し込みを受け付けて、仕事を探す人が求人情報を検索することができます。
厚生労働省によりますと、1か月におよそ7000万件のアクセスがあり、企業が申し込む求人情報のうちおよそ8割がこのサービスを使っているということです。
しかし、利用に必要な情報の入力や求人情報の検索についての質問が多く寄せられているということで、厚生労働省はAIを活用してこうした問い合わせに自動で回答することができないか来年、実証実験を行うことにしました。
期間は1年間を予定していて、厚生労働省では改善点などを調べたうえで、実用化を目指すということです。
2025/05/10
高齢者労災防止を努力義務に フリーランスも保護対象に
働く高齢者の労災防止に向けた作業環境改善を努力義務とする改正労働安全衛生法が、衆院本会議で可決成立しました。同法の保護対象として個人事業主(フリーランス)を位置付けることや、心理的負荷を調べる「ストレスチェック」の全事業所への義務化拡大も柱です。主要部分は2026年4月から順次施行されます。
厚生労働省によると、雇用者全体における60歳以上の割合は23年に18.7%でしたが、休業4日以上の労災に遭った割合は60歳以上が29.3%に上りました。加齢による身体機能の低下が原因とみられ、転落や転倒の事故が多く、休業見込み期間も長引く傾向にあります。
厚労省は20年に高齢者の労災防止に向けたガイドラインを公表しましたが、現場での取り組みは低調です。同省は改正法に基づく指針を策定し、努力義務化により環境改善を促しています。
2025/04/20
基礎年金底上げを法案から削除へ
厚生労働省は年金制度改革法案から、基礎年金の底上げ策を削除する調整入りました。参院選を控え、財源となる厚生年金の減額や、追加の国庫負担が発生することに自民党から反発が出ていました。
公的年金制度は2階建てで、1階の基礎年金はすべての人が加入していますが、基礎年金はこのままだと、財政の悪化で将来にかけて大きく目減りしてしまいます。そこで厚労省は厚生年金を減額して財源をつくり、追加の国庫負担も投入して将来の基礎年金を底上げする改革を検討してきました。
しかし制度上、基礎年金の底上げよりも厚生年金の減額が先行するため、会社員らにとっては当面の間は今の想定に比べ年金額が減ってしまいます。減額幅は最大で月7000円になります。加えて将来的に、基礎年金の国庫負担として最大年2.6兆円の財源を確保しなければなりません。いずれは増税で賄うことが想定されるため、自民党からは批判が出ていました。
2025/04/17
コロナ禍を経て低下した歓迎会・懇親会の開催率、2024年は23.8%
株式会社東京商工リサーチの調査によると、2024年の企業における歓迎会・懇親会の開催率は23.8%と、コロナ禍以降で最低となりました。ここ数年の推移を見ると、コロナ前は51.8%だったものが、コロナ禍の2022年は最低の5.3%まで落ち込み、コロナ禍が落ち着いた2023年は27.9%まで回復しましたが、その後は横ばいから微減となっています。
この結果は、コロナ禍を経て労働者の意識が大きく変化し、従来の慣習にとらわれない働き方や人間関係を求める傾向が強まっていることを示唆しています。コロナ禍のリモートワーク経験は、多くの労働者にとってワークライフバランスを見直す契機となりました。通勤時間の削減や柔軟な働き方は、プライベートの充実や自己啓発に時間を費やすことを可能にし、仕事とプライベートのメリハリを重視する意識が高まっています。
また、ハラスメントに対する意識の高まりも、歓迎会・懇親会の在り方に影響を与えていると考えられます。
2025/03/24
テレワークの実施率が14.6%で過去最低に
日本生産性本部は働く人の意識調査の結果を公表しました。調査によるとテレワークの実施率は14.6%と令和2年からの過去最低を更新しました。年代別では20歳代のみが16.5%と前回調査の14.3%から微増した一方で30歳代以上は減少しています。
テレワークの大多数を占める自宅勤務は実施したくない人が6割以上(63.1%)という結果でした。
調査は雇用者を対象に令和7年1月に実施し、1100名から回答を得ました。
2025/03/16
高ストレス者の睡眠時間は6時間未満
高ストレス者の7割以上は睡眠時間が6時間未満だったことが、健康管理サービスを提供するドクタートラストの調査で明らかになりました。
同社のストレスチェック研究所は平均睡眠時間とストレス度合いの関係を調査したところ、高ストレス者の72.3%が平均睡眠時間が6時間未満だったのに対し、低ストレス者の68%が6時間以上でした。同社では6時間の睡眠確保がストレス予防の目安になるとしています。
2025/03/06
最低賃金1500円に引き上げの政府目標、中小企業の7割超が「不可能」…15%は実現なら「廃業」と回答
日本商工会議所は、最低賃金引き上げの中小企業への影響に関する調査結果を発表しました。2020年代に1500円(全国平均)まで引き上げるという政府の目標について、対応が「不可能」「困難」とする回答は計74・2%に上りました。
政府目標を実現するには、25年度から年率7・3%の引き上げが必要になります。対応可能な年率の引き上げ水準については「1%未満」~「3%程度」が計67・9%を占め、政府目標を満たす「7%程度」と「8%以上」は計1・0%にとどまりました。
想定される影響では、設備投資の抑制など「人件費以外のコストの削減」が39・6%で最も多く、収益悪化で「事業継続が困難(廃業、休業などの検討)」とする回答も15・9%に上りました。
健康保険・介護保険料率が変わります
全国健康保険協会(協会けんぽ)は令和7年度の都道府県別の健康保険料率を決定しました。3月分(4月納付分)から改定されます。
全国平均は10.00%で、最高は佐賀県の10.78%、最低は沖縄県の9.44%です。宮城県は昨年より0.10%アップし、10.11%になります。
なお介護保険料率は全国一律で1.60%から1.59%になります。
2025/02/18
26年10月から パート社会保険料肩代わりで8割還付
厚生労働省はパート従業員の社会保険料を会社が肩代わりできる特例を2026年10月から3年間の時限措置として実施する調整に入りました。肩代わりした保険料の8割を企業に還付する方向です。対象は従業員50人以下の企業などで、財源は社会保険料をあてる考えです。パート労働者の「働き控え」を防ぐのが狙いです。
肩代わりの割合は国の指針に基づいて決まります。例えば、年収106万円の場合は本来労働者50対使用者50の割合を25対75とし、労働者の負担分を月6200円程度減額できるようにします。特例を活用してもパート従業員が将来受け取る年金額には影響ありません。
厚労省は3年以内をめどに賃金要件を無くすほか、27年10月から段階的に企業規模要件を縮小し、35年に撤廃を目指しています。配偶者の扶養から外れて厚生年金に加入する場合、新たに年金や健康保険などの社会保険料を負担するため、手取りが一時的に減少します。
従業員が労働時間を抑制するなど就業調整することが懸念されることから、厚労省は社会保険料の算定基準となる標準報酬月額ベースで年収106万〜151万円程度のパートを対象に、労使折半の保険料負担を企業が一部肩代わりする特例を導入する方向を示していました。
2025/02/05
マイカー通勤手当の非課税額、11年ぶり引き上げ
政府は今年秋にも勤務先から受け取る自動車通勤手当の非課税額を引き上げる方針です。現在は自宅からの距離に応じて最高額が月3万1600円など8区分ありますが、近年のガソリン価格の上昇に対応し、11年ぶりに増額することにします。
所得税法は通勤手当に関して一定額までを非課税とするよう定めています。所得税や住民税の負担額は給与からこの非課税分を除いた額をもとに算出します。
現行制度は自家用車での通勤距離が片道2キロメートル以上10キロ未満の場合、通勤手当の月額から4200円を差し引いた部分に税率をかけて課税額を計算しています。55キロ以上では月3万1600円を非課税としています。
資源エネルギー庁の調査によると、レギュラーガソリンの店頭価格は現在、全国平均で14年1月と比べて2割近く上昇しています。
厚生労働省によると、国内企業の9割超が通勤手当を支給しています。なお国土交通省の調べでは21年時点で、マイカー通勤の割合は三大都市圏で3割ほど、地方都市圏で6割ほどに上っています。
2025/01/30
厚生年金加入の「企業規模」要件の撤廃は2035年に先送り
厚生労働省はパートなど短時間労働者の厚生年金加入拡大に向けた改革を巡り、加入が義務づけられる企業の対象を2027年10月から段階的に広げ、35年10月に企業規模要件を撤廃する方針を固めました。撤廃時期は当初予定では29年10月からにしていましたが、6年間先送りすることになりました。同省は今国会に提出する年金改革関連法案に盛り込むこととしています。
現行の企業規模は「従業員51人以上」としていますが、今後のスケジュールは以下の通りとなります。
・2027年10月「36人以上」
・2029年10月「21人」
・2032年10月「11人以上」
・2035年10月 企業規模要件撤廃
なお加入要件としていた年収「106万円以上」は3年以内に撤廃する予定です。
2025/01/18
厚生年金加入の企業規模要件を段階的に撤廃へ
厚生労働省は、パートなどで働く人が厚生年金に加入できる企業規模の要件について、2年後の10月に現在の従業員51人以上から21人以上に緩和し、4年後の10月に人数要件を撤廃する方向で調整に入りました。
また「年収106万円」の賃金要件はおおむね3年以内に撤廃するとしています。
同省は保険料負担が生じることによる働き控えを防ぐため、労使折半となっている保険料を企業側がより多く負担できる仕組みを設け、一部を企業に還付するなどの支援策も講じる方向で調整しています。
2025/01/18
厚生年金保険料の算定基準を75万円、在職老齢年金基準額は62万円に
厚生労働省は、厚生年金の保険料の算定基準となる標準報酬月額の上限を、2027年9月にも現行の65万円から75万円に引き上げる検討に入りました。
一方一定の給与がある高齢者の厚生年金を減額する「在職老齢年金」(在老)については、26年4月にも減額を始める基準を現行の50万円から62万円に引き上げる方向です。24日に開会する通常国会に提出する改正法案に盛り込む。
会社員らが入る厚生年金の保険料は、現行32等級で区別し、18.3%の保険料率を労使折半で納めています。最も高い区分は65万円ですが、上限を超える高所得者が多いため、75万円に引き上げることとしています。支払う保険料が増えれば、受け取る年金額も増えます。
在職老齢年金の見直しは働くシニア層の就労抑制につながっているとの指摘から見直しが検討されていました。厚労省の試算では、引き上げに伴い新たに約20万人の年金給付が増える見込みです。
2025/01/11
本年1月20日から離職票をマイナポータルで受け取れるようになります
離職後に雇用保険の求職者給付(基本手当等)を受給するために必要となる雇用保険被保険者離職票(以下、「離職票」という)は、離職前の会社を通じ受け取ることになっています。そのため、退職者は会社が離職票発行の手続きをハローワークで行った後に、会社から送付されることを待つ必要がありました。
この手続き(離職票)の流れについて、本年1月20日から、離職者が希望し、一定の条件を満たしたときは、ハローワークでの審査が終了した後に、自動的に離職票等の書類がマイナポータルに送信されることが公表されました。これにより会社から郵送等で送付されることを待つことなく、離職票を受け取ることができ、基本手当等の早期の受給が期待されます。
マイナポータルで受け取るための条件は以下の通りです。
①あらかじめマイナンバーをハローワークに登録していること
②マイナンバーカードを取得し、事前にマイナポータルで雇用保険の連係手続きを行うこと
③事業所が電子申請により雇用保険の離職手続きを行うこと
マイナポータルで被保険者が離職票を受け取る場合は、事業所には離職票のデータは送付されず、離職証明書や資格喪失確認通知書のみが送付されます。
2024/12/21
高額療養費、月8千円引き上げへ
厚生労働省は、医療費の支払いを一定に抑える「高額療養費制度」で、平均的な年収区分としている約370万~770万円の場合、自己負担の上限月額を約8千円引き上げ、約8万8千円とする方向で調整に入りました。上げ幅は10%になります。
医療費が膨らむ中、患者の支払いを増やして医療保険からの給付を抑え、主に現役世代が担う保険料負担を軽減する狙いです。上げ幅は年収に応じて増減させ、住民税非課税の場合は2.7%にとどめます。収入が高い区分は最大15%とします。
2024/12/15
学生バイト 「年収150万円」に引き上げへ
政府・与党は大学生らを扶養する親の税負担を軽減する「特定扶養控除」について、アルバイトなどをする子どもの年収上限を現行の103万円から150万円に引き上げる方向で調整に入りました。2025年からの適用を検討で、25年度税制改正大綱に反映させる考えです。
2024/12/08
年収156万円未満のパート、社会保険料を企業が肩代わり
パート労働者等が厚生年金に加入することで老後の給付が手厚くなる半面、保険料負担で手取り収入が減るといった課題があります。そのため厚労省は年収156万円未満の人に限り、保険料の一部を企業の判断で肩代わりできる仕組みを時限的な措置として検討しています。
企業が肩代わりする割合は任意で設定できますが、全額を負担することは認めないことにしています。肩代わりを受けても将来の年金額は変わりません。
ただ中小企業を中心に「経営体力のある大企業しか活用できず、待遇格差を招く」との批判があり、負担増となる企業への支援策も用意する方針です。
2024/12/08
106万円の壁、26年に撤廃へ 厚生年金、パート加入拡大
厚生労働省は、会社員に扶養されるパートら短時間労働者が厚生年金に加入する年収要件(106万円以上)を2026年10月に撤廃する方向で調整に入りました。保険料負担を避けるため働く時間を抑制する「106万円の壁」とされてきました。勤務先の従業員数が51人以上と定めている「企業規模要件」も27年10月に撤廃し、週の労働時間が20時間以上の人は年収や企業規模を問わず厚生年金に加入することになります。
2024/11/21
働く高齢者の年金減「緩和」へ
厚生労働省は、働いて一定の収入がある高齢者の厚生年金を減らす「在職老齢年金制度」を見直し、対象を縮小する方向で調整に入りました。これにより働きながら年金を満額受け取れる高齢者が増えることになります。「働き損」を解消して就労を促し、人手不足の緩和につなげる考えです。現在は賃金と年金の合計が月50万円(基準額)を上回った分の半額を減らす仕組みになっています。この基準額を62万円や71万円に引き上げる案を軸としています。与党との協議も経て年末までに決める予定です。
2022年度末時点で働きながら年金を受給する65歳以上は約308万人。うち約50万人が当時の基準額(47万円)を超えていました。減らした総額は年間4千億円以上で就労意欲を阻害しているとの指摘がありました。
2024/11/13
副業促進へ、割増賃金の「労働時間通算ルール」見直し検討
会社員などの副業に関し、1日8時間、週40時間を超えて働いた分に支払う割増賃金を計算する際に、本業先と副業先の労働時間を合算するという現行制度の見直しを厚生労働省が検討しています。
複雑な現行ルールを見直して企業側の負担を減らし、副業を促すのが狙いです。
労基法上、1日8時間、週40時間の法定労働時間を超えて働かせる場合は、労使協定を結び割増賃金を支払う必要があります。
現在の副業のルールでは、ある企業で雇用する従業員が副業先でも雇用されて働く場合、自社と副業先の労働時間を足して労働時間を把握し、割増賃金を支払う必要があります。1日単位で把握する必要がある上、どちらの雇用契約が先かなどを考慮しなければならず、複雑な制度になっています。
ただし、労働時間の合算は健康管理の目的もあるため、厚労省は長時間労働とならないよう通算した労働時間を把握する仕組み自体は残し、割増賃金の支払いでは適用しない方法などを検討しています。
2024/11/13
労働者の連続勤務14日以上禁止へ
厚生労働省の専門家らによる研究会で、14日以上の連続勤務を禁止するために法改正を検討すべきとの骨子案が示されました。
労働基準法では週に一日以上の休日を原則として、週休制が難しい場合は例外的に4週間を通じて4日以上の休日を確保することを企業などに義務付けています。
この制度では最長で48日間の連続勤務が可能となることから、厚労省の研究会では14日以上の連続勤務の禁止を検討すべきとする報告書の骨子案が示されました。
労災認定の基準である「2週間以上の連続勤務」を防ぎ、労働者の健康を確保したいとしています。
今後、来年の審議会でも議論を進め、労働基準法の改正につなげたい考えです。
2024/11/09
厚生年金加入「106万円の壁」撤廃へ
厚生労働省は、会社員に扶養されるパートら短時間労働者が厚生年金に加入する年収要件(106万円以上)を撤廃する方向で最終調整に入りました。勤務先の従業員数を51人以上とする企業規模の要件もなくす方針です。これにより週の労働時間が20時間以上あれば、年収を問わず加入することになります。老後の給付を手厚くする狙いですが、保険料負担が生じることになります。厚生年金の年収要件は「106万円の壁」と呼ばれ、保険料負担を避けるため働く時間を抑制する要因ともされてきました。
一方、政府与党は国民民主党の主張を踏まえ、年収が103万円を超えると所得税が発生する「年収の壁」を見直し、非課税枠の引き上げを検討中です。これに対し厚生年金の年収要件をなくせば、手取り収入が減ることになり、曲折も予想されます。
最低賃金の引き上げに伴い、週20時間以上の労働時間があれば年収106万円を上回る地域が増えており、厚労省は実態に合わせて撤廃すべきだと判断しました。来年の通常国会に関連法案提出を目指します。